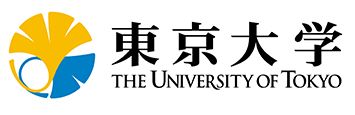研究
シンポジウム
第33回身体運動科学シンポジウム(2025年度)(福井尚志教授退職記念)
| ジュニアから高齢者までを見据えたスポーツ医学の最前線 |
| 2025年11月29日(土):13時-16時30分(ポスター) 東京大学 駒場Iキャンパス18号館1階ホール 共催:東京大学 スポーツ先端科学連携研究機構(UTSSI) |
| 第一部 (13:00-15:05) |
| 「なぜ骨格筋は弱るのか?活性酸素や代謝から読み解くサルコペニア」 |
| 門口 智泰(東京大学大学院総合文化研究科 助教) |
| 「ジュニアトップアスリートにおけるスポーツ損傷調査」 |
| 今井 一博(東京大学大学院総合文化研究科 准教授) |
| 「運動器治療・予防から「ヘルスプロモーション」に向けて:身体活動・スポーツ心身データDXからメタバース・デジタルツイン活用」 |
| 中田 研(大阪大学大学院医学系研究科 教授) |
| 第二部 基調講演(15:15-16:30) |
| 「私の軌跡と現在地」 |
| 福井 尚志(東京大学大学院総合文化研究科 教授) |
| 報告記: こちら |
第32回身体運動科学シンポジウム(2024年度)(八田秀雄教授退職記念および最終講義)
| 常識にとらわれない身体運動科学 |
| 2024年12月14日(土):13時-16時30分(ポスター) 東京大学 駒場Iキャンパス13号館1323教室 共催:東京大学 スポーツ先端科学連携研究機構(UTSSI) |
| 第一部 (13:00-15:05) |
| 「骨格筋ミトコンドリアの適応を誘導する代謝シグナルとしての乳酸」 |
| 高橋 謙也(東京大学大学院総合文化研究科 助教) |
| 「骨格筋代謝調節におけるPPAR/δの役割」 |
| 寺田 新(東京大学大学院総合文化研究科 教授) |
| 「運動後のグリコーゲン回復 「合成する」以外にも目を向けて」 |
| 高橋 祐美子(東京大学大学院総合文化研究科 准教授) |
| 「強化の現場で活用する乳酸の新しい可能性を求めて」 |
| 柿木 克之(Blue Wych合同会社代表) |
| 第二部 基調講演(15:10-16:30) |
| 「乳酸は疲労物質でないと言い続けて40年」 |
| 八田 秀雄(東京大学大学院総合文化研究科 教授) |
| 報告記: こちら |
第31回身体運動科学シンポジウム(2023年度)
| ストレッチングの最新研究動向 |
| 2023年11月25日(土):13時-15時30分 Zoomウェビナー 共催:東京大学 スポーツ先端科学連携研究機構(UTSSI) |
| 13:00 開会挨拶 久保啓太郎(東京大学 大学院総合文化研究科 教授・身体運動科学研究室主任) |
| 13:05 身体運動科学研究室・スポーツ先端科学連携研究機構紹介 吉岡伸輔(同 准教授・広報) |
| 13:15 シンポジウム趣旨説明 進行役:久保啓太郎 |
| 講演 第一部 |
| 13:25 ストレッチングが筋構造・力学的特性に及ぼす効果:現場に還元するためのエトセトラ」 |
| 中村雅俊(西九州大学 准教授) |
| 13:45 筋柔軟性改善や肉離れ予防のためのストレッチング |
| 宮本直和(順天堂大学 先任准教授) |
| 14:05 腱特性変化からみたストレッチングの是非 |
| 久保啓太郎(東京大学 教授) |
| 講演 第二部 |
| 14:35 パフォーマンス向上のためのストレッチング再思三考 |
| 山口太一(酪農学園大学 教授) |
| 14:55 動脈硬化予防・改善に効果的なストレッチングとは? |
| 家光素行(立命館大学 教授) |
| (各講演:15分発表&5分質疑) |
| 総合討論 |
| 15:15- 総合討論 |
| 報告記: こちら |
第30回身体運動科学シンポジウム(2022年度)
| 骨格筋・代謝からみる身体運動科学 |
| 2022年11月23日(水):13時-15時30分
(ポスター) Zoomウェビナー 共催:東京大学 スポーツ先端科学連携研究機構(UTSSI) |
| 主旨: 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、多くの人の生活習慣、特に食生活や身体活動量・運動習慣に変化が生じたと思われます。骨格筋をはじめとした身体組織の代謝機能は生活習慣による影響を受けやすく、その機能低下は数々の疾患のもととなります。その一方で、食生活の改善や運動の実施などにより、すみやかに改善されます。本シンポジウムでは、骨格筋・代謝分野の若手研究者の発表をきっかけに、現在そして未来の健康について、参加者の皆様と共に考えていければと思います。 |
| 講演 |
| 「性腺機能低下症モデルから考えるエネルギー代謝の性差」 |
| 高橋 謙也 (東京大学 大学院総合文化研究科 助教) |
| 「活性酸素種や脂肪酸代謝産物はサルコペニアに関連するか?」 |
| 門口 智泰 (東京大学 大学院総合文化研究科 助教) |
| 「トレーニング休止に伴う骨格筋ミトコンドリアの変化と分岐鎖アミノ酸摂取の影響」 |
| 松永 裕 (東京大学 大学院総合文化研究科 助教) |
| 「糖質の摂取習慣が骨格筋を中心としたエネルギー代謝に与える影響」 |
| 高橋 祐美子 (東京大学 大学院総合文化研究科 准教授) |
| 総合討論 |
| 進行役:八田秀雄(東京大学 大学院総合文化研究科 教授) |
| 報告記: こちら |
第29回身体運動科学シンポジウム(2021年度)
| 身体運動のニューロサイエンス |
| 2021年9月25日(土):13時-16時30分(ポスター) Zoomウェビナー 共催:東京大学 スポーツ先端科学連携研究機構(UTSSI) |
| 主旨: このシンポジウムでは、スポーツ上達の科学やリハビリテーション科学とは少し違った視点から「身体運動のニューロサイエンス」に迫ります。具体的には、我々が日頃から何気なく行っている基本動作の神経調節メカニズムに始まり、自分さらには他人の行動に影響を与える脳の話、そして身体をどこまで自在に操れるかという人間拡張技術の紹介まで、この分野の最前線に立つ研究者をお招きしてそれぞれ旬なトピックを語っていただきます。 |
| 第1部 13:00-14:30 若手研究者が紹介するニューロサイエンス研究の最新トピック |
| 「予測的姿勢制御における新たな実験課題と数理シミュレーション」 |
| 鴻巣 暁(東京大学大学院総合文化研究科 身体運動科学研究室 助教) |
| 「非侵襲神経機能計測によるヒト歩行制御の神経基盤の理解」 |
| 横山 光(東京大学大学院総合文化研究科 身体運動科学研究室 助教) |
| 「他人とシンクロする身体・脳」 |
| 宮田 紘平(東京大学大学院総合文化研究科 身体運動科学研究室 助教) |
| 「行動から脳のはたらきを科学する」 |
| 結城 笙子(東京大学大学院総合文化研究科 身体運動科学研究室 助教) |
| 第2部 14:40-16:30 ニューロサイエンス研究の広がりと今後の展望 |
| 「ヒト睡眠ダイナミクスの機序解明と操作への展望」 |
| 岸 哲史(東京大学大学院教育学研究科 身体教育学講座 助教) |
| 「ヒトに寄り添い,ヒトを高める,人間拡張技術」 |
| 村井 昭彦(産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 主任研究員) |
| 「身体とこころの相互作用と人間拡張」 |
| 鳴海 拓志(東京大学大学院情報理工学系研究科 人間機械情報学講座 准教授) |
| 総合討論 |
| 進行役:中澤 公孝(東京大学大学院総合文化研究科 身体運動科学研究室 教授/UTSSI 機構長) |
| 報告記: 教養学部報 第633号 |
第28回身体運動科学シンポジウム―深代千之教授退職記念(2020年度)
| スポーツ動作分析とバイオメカニクスの未来 |
| 2021年1月23日(土):13時-16時00分 Zoomウェビナー(ポスター) |
| 主旨: スポーツ競技においてアスリートがみせる難度の高い動き、洗練された動き、時に想像を超える動きに人々は魅了されます。バイオメカニクスは、それらの魅力の背景にあるスポーツや身体運動の仕組みについて、力学をはじめとした物理/数学的手法を用いて解明する研究分野です。本シンポジウムでは、スポーツ動作分析およびバイオメカニクスの未来について、最新の研究知見に加えて、バイオメカニクスの研究史を振り返りながら考えます。第一部では、本学名誉教授・深代千之が分野の魅力や研究史の話題も交えながらバイオメカニクスの意義、そして今後の応用について講演いたします。第二部では、5名の研究者が最新の研究知見を紹介した上で、参加者の皆様と共にスポーツ動作分析とバイオメカニクスの未来について考えます。 |
| 総合司会:竹下大介(東京大学大学院総合文化研究科准教授) 13:00~ 主任挨拶 柳原大(東京大学 大学院総合文化研究科 教授) |
| 第1部 基調講演 |
| 13:05~ 演者紹介 竹下大介 |
| 13:10~ 「バイオメカニクスの魅力と応用」 |
| 深代千之(日本女子体育大学学長、東京大学名誉教授、日本体育学会会長、日本バイオメカニクス学会会長 |
| 14:10~ 休憩 |
| 第2部 スポーツ動作分析とバイオメカニクスの未来 |
| 14:20~ 「新たな動作解析手法の提案」 |
| 長野明紀(立命館大学スポーツ健康科学部 教授) |
| 14:35~ 「最新の跳ぶ科学:下肢の伸展動作に留まらない巧みな全身動作としての跳躍」 |
| 佐渡夏紀(早稲田大学スポーツ科学学術院 助教) |
| 14:50~ 「卓球のフォアハンドストロークにおける動作の再現性を高めるための冗長性の利用」 |
| 飯野要一(東京大学大学院総合文化研究科 助教) |
| 15:05~ 「トッププロゴルファーのデータから考える動作の再現性」 |
| 吉岡伸輔(東京大学大学院総合文化研究科/スポーツ先端科学連携研究機構 准教授 |
| 15:20~ 「上肢障がいを有するテコンドー選手の蹴り動作遂行における主観と客観」 |
| 木下まどか(東京大学 大学院総合文化研究科 助教) |
| 15:35~ 総合討論 |
| 報告記: 教養学部報 第627号 |
第27回身体運動科学シンポジウム(2019年度)
| 新時代における骨格筋とトレーニングの科学 |
| 2019年7月13日(土):12時-16時30分 東京大学駒場キャンパス 21 KOMCEE West レクチャーホール(アクセス)(ポスター、抄録集) |
| 主旨: 記念すべき第1回の身体運動科学シンポジウムが開催されたのは 平成初期(1993年6月)のことであり、その時のテーマは「ヒトの筋のダイナミックス」であった。 それから約26年の歳月を経て、新しい時代を迎えた今もなお、筋(骨格筋)は身体運動科学研究において欠かせないキーワードである。 むしろ、超高齢社会の到来や東京オリンピック・パラリンピック大会の開催などを受けて、骨格筋やそのトレーニング方法への社会的関心はますます高まっているのではないだろうか。 そこで、令和最初の身体運動科学シンポジウムでは原点に立ち返り、各演者が骨格筋をキーワードに最新の研究成果を紹介するとともに、今後の骨格筋研究の展望について議論する。 また、あわせて行うポスターセッションでは大学院生が中心となり、身体運動科学研究室の多様で独創的な研究内容を紹介する。 |
| 12:00~ ポスターセッション |
| 13:00~ 主任挨拶 柳原大(東京大学 大学院総合文化研究科 教授) |
| 第1部 基調講演 |
| 13:05~ 演者紹介 福井尚志(東京大学 大学院総合文化研究科 教授) |
| 13:10~ 「筋トレーニング研究の未来」 |
| 石井直方(東京大学 大学院総合文化研究科 教授) |
| 14:10~ ポスターセッション&コーヒーブレイク |
| 第2部 健康長寿社会の実現を支える骨格筋の基礎研究 |
| 14:40~ 「レジスタンス運動のプロトコルと効果の関係性について」 |
| 小笠原理紀(名古屋工業大学 生命・応用化学専攻 准教授) |
| 15:00~ 「筋萎縮の原因とレジスタンス運動を用いた予防について」 |
| 中里浩一(日本体育大学 保健医療学部 教授) |
| 15:20~ 「温熱刺激による骨格筋ミトコンドリアの適応と加齢関連疾患治療への応用」 |
| 田村優樹(日本体育大学 体育学部 助教) |
| 15:40~ 「レジスタンス運動直後における筋疲労度と長期効果の関連」 |
| 佐々木一茂(東京大学 大学院総合文化研究科 准教授) |
| 16:00~ 総合討論 |
第26回身体運動科学シンポジウム(2018年度)
| Sciences for Human performance |
| 2018年5月19日(土)シンポジウム:9時-11時45分 東京大学本郷キャンパス 伊藤国際学術研究センター地下2階 伊藤謝恩ホール(アクセス) 共催:スポーツ先端科学研究拠点 |
| 主旨: 東京大学スポーツ先端科学研究拠点と身体運動科学研究室は、スポーツや日常生活におけるヒューマン・パフォーマンスの理解を目指したシンポジウムを開催いたします。 シンポジウム1では、『ヒューマン・パフォーマンスの基礎とサポート ー若手研究者による最新研究からー』をテーマとして、東京大学にて学位取得後、 スポーツ・身体運動の研究分野で研究者として活躍する若手OB・OGによる研究知見を分野横断的に紹介します。ヒューマン・パフォーマンスに関わる研究について 俯瞰的に知ることのできる内容となっております。 シンポジウム2では、『モータースポーツから考えるヒューマン・パフォーマンス ー運転技術とは?ー』をテーマとして、議論を行います。昨今、運転の自動化の話題が隆盛です。 しかしながら、通常の人操作による運転についても、運転技術の構成要素やドライバーに求められる技能について、不明な点が多いのが現状です。 そこで、各種技術の粋が集まるモータースポーツを題材に、運転技術について考えます。世界最高の女性レーシングドライバーである井原慶子氏、 認知科学分野の研究者である工藤和俊氏、工学分野の研究者である中野公彦氏の3名にて、運転技術の構成要素やドライバーに求められる技能などについて多面的に議論を行います。 大学・研究関係の皆様はもちろんのこと、五月祭にお越し予定の皆様方におかれましても、お気軽にお立ち寄りください。 |
| 9時-10時20分 |
| 第1部 ヒューマン・パフォーマンスの基礎とサポート ー若手研究者による最新研究からー |
| ・応用科学としてのヒト骨格筋研究 |
| 佐々木一茂(日本女子大学家政学部 准教授) |
| ・エリートアスリートのサポートにおけるスポーツ科学と研究 |
| 稲葉優希(ハイパフォーマンスセンター・国立スポーツ科学センター スポーツ科学部・機能強化ユニット 研究員) |
| ・運動後の骨格筋グリコーゲン回復促進 -『刀』は一つではない?- |
| 高橋祐美子(東京大学大学院総合文化研究科・身体運動科学 助教) |
| ・心拍制御の研究から精神疾患研究まで -心の解明を目指して- |
| 古田島浩子(公益財団法人東京都医学総合研究所 精神行動医学研分野 依存性薬物プロジェクト 研究員) |
| 10時30分-11時45分 |
| 第2部 モータースポーツから考えるヒューマン・パフォーマンス -運転技術とは?- |
| ・安全運転のためのドライバーの生体情報に基づく集中力と感情のコントロール |
| 井原慶子(レーシングドライバー、FIA国際自動車連盟アジア代表委員) |
| ・ドライビングの知覚と行為 |
| 工藤和俊(東京大学大学院情報学環・学際情報学府 准教授) |
| ・ドライバの表面筋電図による車両運動性能の評価 |
| 中野公彦(東京大学大学院情報学環・学際情報学府 准教授 |
| 報告記: 教養学部報 第603号 |
第25回身体運動科学シンポジウム(2017年度)
| 若手研究者による身体運動科学研究、現在から未来 |
| 2017年6月3日(土) 13時-17時 東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE West レクチャーホール 共催:スポーツ先端科学研究拠点 |
| ・アスリートの心理状態を捉える -ウェアラブルセンサを活用した非侵襲無拘束計測とその応用- |
| 井尻哲也 |
| ・身体運動における姿勢の安定化と動きの良さの評価 |
| 田辺弘子 |
| ・ヒトのロコモーションに内在する神経機構の課題特異性 -行動科学的側面からの考察- |
| 小川哲也 |
| ・適応的な歩行に潜む制御メカニズムの本質的理解 -数理モデルによる理論化に向けて- |
| 藤木聡一朗 |
| ・運動後の骨格筋グリコーゲン回復を促進させる栄養素とは? |
| 高橋祐美子 |
| 報告記: 教養学部報 第595号 |
第24回身体運動科学シンポジウム(2016年度)
| 東京大学スポーツ先端科学研究拠点構想と東京オリンピック・パラリンピック |
| 2016年6月4日(土) 13時00分-17時20分 東京大学駒場キャンパス 教養学部900番教室(講堂) 主催:東京大学大学院総合文化研究科、同研究科身体運動科学研究室 |
| 拠点開設記念式典 |
|
司会: 内山融 東京大学大学院総合文化研究科教授 開式演奏(オルガン独奏): 中川 岳 東京大学教養学部教養学科 主催者挨拶: 小川桂一郎 東京大学大学院総合文化研究科長 拠点長挨拶: 石井直方 東京大学大学院総合文化研究科教授 総長挨拶: 五神真 東京大学総長 来賓祝辞: 遠藤利明 東京オリンピック・パラリンピック担当大臣 来賓祝辞: 馳浩 文部科学大臣 来賓祝辞: 大東和美 日本スポーツ振興センター理事長 パネルディスカッション 「社会を駆動するスポーツの力」 (モデレーター:小林 至 江戸川大学教授) |
| 五神真、遠藤利明、馳浩、田口亜希(パラリンピック射撃競技日本代表) |
| シンポジウム 第1部 スポーツ・健康科学の基礎と応用 |
| ・筋機能の基礎科学とその応用 |
| 石井直方 東京大学大学院総合文化研究科教授 |
| ・パラリンピックブレイン -パラアスリートの脳にみる可能性- |
| 中澤公孝 東京大学大学院総合文化研究科教授 |
| ・乳酸を中心に考える運動時のエネルギー代謝 |
| 八田秀雄 東京大学大学院総合文化研究科教授 |
| ・動きの解析から動きの創造へ |
| 深代千之 東京大学大学院総合文化研究科教授 |
| シンポジウム 第2部 スポーツ科学とオリンピック・パラリンピック |
| ・日本におけるスポーツ医・科学 |
| 川原 貴 国立スポーツ科学センター長 |
| ・外傷・障害に対する医科学サポート |
| 福井尚志 東京大学大学院総合文化研究科教授 |
| ・パネルディスカッション (モデレーター:石井直方) |
| 川原 貴、 福井尚志、井上康生(柔道日本代表チーム監督)、 根木慎志 シドニーパラリンピック男子車椅子バスケットボール日本代表キャプテン |
| 報告記: 教養学部報 第586号、 スポーツ先端科学研究拠点HP |
第23回身体運動科学シンポジウム(2015年度)
| 運動・トレーニングの効果に関わる物質と栄養 |
| 2015年6月6日(土)ポスター発表:11時から、シンポジウム:13時-16時 東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE East 大ホール(K011) |
| ・イントロダクション:トレーニング効果の物質的基盤 |
| 石井直方 |
| ・骨格筋ミトコンドリア新生に関わる物質と栄養 |
| 北岡祐 |
| ・骨格筋量調節に関わる物質と栄養 |
| 小笠原理紀 |
| ・脂質によってパフォーマンスは向上するのか? ?スポーツ栄養学の新たな可能性? |
| 寺田新 |
| ・運動スキルの神経基盤と関連する脳内栄養物質 |
| 柳原大 |
| ・パネルディスカッション |
| 報告記: 教養学部報 第577号 |
第22回身体運動科学シンポジウム(2014年度)
| 常識を打ち破る最新スポーツ科学 |
| 2014年7月12日(土)13:00-17:00 東京大学駒場キャンパス 13号館 1323教室 |
| ・乳酸はアスリートにとって敵?それとも味方? |
| 北岡祐 |
| ・運動による筋サイズ調節の科学-常識を覆す最新エビデンス- |
| 小笠原理紀 |
| ・スキー研究へのチャレンジ |
| 吉岡伸輔 |
| ・熟達化のダイナミクス |
| 工藤和俊 |
| ・小学生でも150kmを打てる? |
| 中澤公孝 |
| ・野球界の常識を疑え! |
| 桑田真澄 |
| ・総合討論 |
| 報告記: 教養学部報 第568号 |
第21回身体運動科学シンポジウム(2013年度)
| スポーツ障害とバイオメカニクス 最前線 |
| 2013年6月29日(土)ポスター発表:12時から、シンポジウム:13時-17時 東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE レクチャーホール |
| ・ヒト直立姿勢の冗長な多関節制御 |
| 笹川俊 |
| ・日常生活における筋パフォーマンス評価 |
| 吉岡伸輔 |
| ・クラシックバレエの回転動作におけるバランス調整の方法について |
| 井村祥子 |
| ・ソフトボールのバッティングにおける腰の回転の力学 |
| 飯野要一 |
| ・スポーツ競技におけるスポーツ医科学支援 |
| 今井一博 |
| ・スポーツ障害の克服に向けて -靱帯損傷への挑戦- |
| 福井尚志 |
| ・動きの本質を究明するバイオメカニクス |
| 深代千之 |
| ・シンポジウム総合討論 |
| 報告記: 教養学部報 第560号 |
第20回身体運動科学シンポジウム(2012年度)
| 身体運動科学 ―これまでの歩みとこれからの10年― |
| 2012年6月30日(土)ポスター発表:12時から、シンポジウム:13時-17時 東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE レクチャーホール |
| ・膝蓋腱およびアキレス腱における血液循環の差異と可塑性との関連性 |
| 久保啓太郎 |
| ・変形性関節症研究の最前線 -病態解明から新しい治療へ- |
| 福井尚志 |
| ・レジスタンストレーニングの科学 -この10年の変遷とこれから- |
| 石井直方 |
| ・さきがけバイオメカニクス |
| 深代千之 |
| ・投球動作における体幹近位の身体セグメントの減速がボール速度に及ぼす影響 |
| 小嶋武次 |
| ・巧みさと上達の科学 |
| 工藤和俊 |
| ・ニューロリハビリテーションと身体運動科学-これからの10年- |
| 中澤公孝 |
| ・運動の制御、学習、予測における小脳皮質のはたらき:遺伝子改変動物とヒトを対象にして |
| 柳原大 |
| ・身体運動に対する骨格筋代謝機能の適応機構の解明とExercise mimeticsへの挑戦 |
| 寺田新 |
| ・糖と乳酸から考える身体運動 |
| 八田秀雄 |
| 報告記: 教養学部報 第550号 |
第19回身体運動科学シンポジウム(2011年度)
| 身体運動と運動器の科学―最前線― |
| 2011年7月2日(土)ポスター発表:12時から、シンポジウム:13時-16時30分 東京大学駒場キャンパス アドニミストレーション棟3階 学際交流ホール |
| 主旨: 身体運動は全て、脊髄運動ニューロンからのインパルスが筋を収縮させ、腱を介して骨を動かし、関節運動を引き起こすことで発現する。 このプロセスにおいて神経からの指令を受け最終的に運動を引き起こす組織、すなわち筋、腱、骨などに代表される組織を運動器という。 身体運動科学において運動器は研究のまさに主役たる組織である。今回の公開シンポジウムでは、この運動器をテーマとして、 細胞レベルからアスリートの身体まで、様々な視点から各シンポジストが最新の研究成果を紹介する。さらにポスターセッションにおいては 東京大学総合文化研究科生命環境科学系身体運動科学研究室所属の大学院生を中心に日頃の研究成果を報告する。 これらの研究発表を通じ、参加者とポスター発表者、講演者の間の活発なディスカッションと情報交換が行われることを期待する |
| ・高強度インターバルトレーニングによる骨格筋エネルギー代謝の適応 |
| 星野太佑 |
| ・骨格筋における電気力学的遅延を再考する |
| 佐々木一茂 |
| ・筋力トレーニングおよび脱トレーニングに伴う筋・腱特性変化のタイムコース |
| 久保啓太郎 |
| ・トップアスリートの身体スキル |
| 工藤和俊 |
| ・接着分子を介した軟骨細胞の制御 |
| 福井尚志 |
| ・シンポジウム総合討論 |
| 報告記: 教養学部報 第541号 |
第18回身体運動科学シンポジウム(2010年度)
| トップアスリートの科学 |
| 2010年10月23日(土)ポスター発表:12時から、シンポジウム:13時-17時 東京大学駒場キャンパス 数理科学研究科棟大講義室 |
| 主旨: “トップアスリートがトップアスリートである所以を科学的に解き明かす”、これは身体運動を科学する者ならば誰もが、多かれ少なかれ心のどこかに持つ野心的課題である。 しかしトップアスリートを対象とする研究は、対象がトップアスリートであるがゆえ、1 例あるいは数例の特異な例を提示することにとどまらざるを得ない。 そこから一般法則を導くのは至難の業である。それでもトップアスリートは常に私たちの探究心をそそる魅力的な存在であり続ける。 今回のシンポジウムでは、“トップアスリートの科学”をテーマとして、関連する研究者に話題を持ち寄っていただいた。 とりわけ、早稲田大学の彼末先生には、難解な野球のスキルに対し、見事な切り口で科学のメスを入れた最新の研究成果をご紹介していただけることとなった。 参加者の方々には、科学的視点から見たときのトップアスリートの凄さ、さらにはトップアスリートをサポートする科学、それらの最新の動向を堪能していただければ幸いである。 |
| ・招待講演「野球を科学する― 解析の新しい切り口―」 |
| 彼末一之 (早稲田大学スポーツ科学学術院 教授) |
| ・バレエにおける連続回転の仕組み~フェッテターンの動作分析 |
| 井村祥子 |
| ・北京五輪に向けて行ったソフトボール女子日本代表に対する科学的取り組み |
| 千野謙太郎 |
| ・競歩選手における生理学的特性と高地トレーニングの効果 |
| 禰屋光男 |
| ・スキージャンプ金メダリストのバランス感覚 |
| 工藤和俊 |
| ・血中乳酸濃度測定の生かし方 |
| 八田秀雄 |
| ・シンポジウム総合討論 |
第17回身体運動科学シンポジウム(2009年度)
| 直立二足歩行を考える-健康スポーツ医学・身体運動科学から |
| 2009年7月11日(土)ポスター発表:13時から、シンポジウム:14時-17時 東京大学駒場キャンパス アドニミストレーション棟3階 学際交流ホール |
| ・はじめに 健康スポーツ医学より現代人の問題点 |
| 座長 久保田俊一郎教授 |
| ・講演1:立つ、歩くために必要な神経機構-遺伝子変異マウスを用いた研究より |
| 柳原大 |
| ・講演2:立つ、歩くために必要な 筋力、トレーニング |
| 石井直方 |
| ・講演3:立つ、歩くことが障害された状態、ロコモティブ症候群 -スポーツ障害から変形性関節症まで- |
| 渡會公治 |
| ・講演4:再び立つ、歩くためのリハビリテーション科学 |
| 中澤公孝 |
| ・総合討議:直立二足歩行を考える-健康スポーツ医学・身体運動科学から 文系のコメンテーターの感想、質疑 |
| 菅原克也 教授(超域文化/英語) |
第16回身体運動科学公開シンポジウム(2008年度)
| 力と動きのコラボレーション |
| 2008年11月8日(土)ポスター発表:12時から、シンポジウム:13時45分-17時 東京大学駒場キャンパス 数理科学研究科大講義室 |
| 主旨: 人間の活動の原点は筋の発揮する力であり、その力を活動の目的に応じたさまざまな動きに巧みに活用することによって、 スポーツや労働や日常生活におけるさまざまな身体活動のコストパフォーマンスを向上させ、合理的かつ効果的な行動を実行することができる。 また、身体の動きは体組織の力伝達系を介して一つ一つの細胞の内部にまで伝わることによって、その活性にさまざまな影響を及ぼす。 一方、動きに合致しない不自然な力の付加や力の特性に合致しない不合理な動きを行なえば、所期の目的を達成できないばかりか、障害の危険も生じる。 このような観点から、本シンポジウムでは、ヒトの生活やスポーツパフォーマンスの原点である筋力と動きの協調について考える。 |
| ・力から神経・筋の機能を探る |
| 佐々木一茂 |
| ・筋腱複合体の構造と機能 |
| 深代千之 |
| ・筋・腱の動きが体細胞の機能に与える影響 |
| 新井秀明 |
| ・スポーツスキルのバイオメカニクス |
| 小嶋武次 |
| ・卓球の動作解析 |
| 飯野要一 |
| ・筋力のバランスがスポーツパフォーマンスに与える影響 -陸上競技長距離種目とフェンシングのケース- |
| 松垣紀子 |
| ・シンポジウム総合討論 |
第15回身体運動科学公開シンポジウム(2007年度)
| 身体のサステイナビリティ ~脳と身体の健康のために~ |
| 2007年12月1日(土)ポスター発表:12時から、シンポジウム:13時45分-17時 東京大学駒場キャンパス 数理科学研究科大講義室 |
| 主旨: 有限な天然資源の持続的有効利用のために、地球環境のサステイナビリティ(持続可能性)の確保は人類共通の重要課題となっている。 東京大学アクションプラン2007 は、自律分散協調系と知の構造化をキーワードとして、環境を保全し、自然と人工の調和を保ちつつ、 生態系の中で人間社会の発展と繁栄がいつまでも持続するように、地球規模の新しい知のパラダイムとして、サステイナビリティ学の創成を謳っている。 人類が生存し繁栄を続けるためには、人類をとりまく環境を改善すると同時に、人類自体をも持続可能な生命体として保全する必要がある。 健全な身体と健全な精神を育成し、次世代に引き継ぐことは、人類自身のサステイナビリティにとって根源的な重要性をもっている。 本シンポジウムでは、生物としてのヒトに焦点をあて、その持続可能性について今日的視点から再考する。 |
| ・乳酸からみた持久力とサステイナビリティ |
| 八田秀雄 |
| 【要旨】乳酸は長い間、疲労の素になる老廃物とされてきたが、最近では、 実は乳酸以外の原因で生じる疲労も多く、乳酸は筋における糖の利用を促進する重要なエネルギー源であることがわかってきた。 そうした新しい乳酸の見方から運動の持久力とその健康への関わりを再考する。 |
| ・スポーツ選手の持久性トレーニング |
| 禰屋光男 |
| 【要旨】陸上競技の長距離選手のように長時間の運動を行う競技選手ではいわゆる持久力が競技成績に直結する。 持久性能力をより向上させるために、通常より酸素の薄い厳しい環境である高地で行なわれる高所トレーニングの理論と実際を解説する。 |
| ・スポーツ障害治療から障害予防、サステイナビリティをめざす |
| 渡會公治・伊藤博一 |
| 【要旨】スポーツ障害は、使いすぎばかりでなく、身体構造上無理な使い方によっても生じる。 肩や肘の痛みなどの投球障害に関する我々の研究を例に、本来機能と切り離せない身体の構造を理解し正しく機能させる工夫・技術による、障害のない快適な身体活動継続の方策を探る。 |
| ・こころ・ストレス・からだ |
| 村越隆之 |
| 【要旨】様々な種類のストレスから精神的身体的変化が引き起こされる。これは心と体が脳を介して関係し合っている事の現れである。 神経系がストレスを情報として処理するメカニズムを解析し、客観的なストレス対応の可能性を探る。 |
| ・身体運動と脳の相互作用:運動は知性を向上させるか? |
| 柳原大 |
| 【要旨】最近の神経科学は、身体運動が、筋・心臓・呼吸器のみならず、運動を制御する脳に対しても大きな改善効果を及ぼすことを明らかにしている。 それらの研究成果とその生理学的メカニズムを考察する。 |
| ・シンポジウム総合討論 |
第14回身体運動科学公開シンポジウム(2006年度)
| ARTする身体 |
| 2007年1月27日(土)ポスター発表:11時30分-13時10分、シンポジウム:13時20分-18時30分 東京大学駒場キャンパス 数理科学研究科大講義室 |
| 主旨: 人間は、体を使って生活し、遊び、表現し、文化を創造してきた。体の動きは、遺伝子情報を読み出しつつ生きる自律的生命体としての「ヒト」が「人間」になるために不可欠な行為であり、 その基盤には巧妙な生命進化の 技(art)が潜んでいる。自己と他者のコミュニケーションを行なうために、心を言葉にするのも、言葉を文字にするのも、また文字を言葉にするのも、 すべて、言語を介さない自己表現と同様、身体の巧みな動きというartによっている。そして、言語・非言語を問わず、個人の技芸は次第に体系化され一般性のある技術を産み出してきた。 その背景には、常によりよい技を求めて合理性を追求し続けた、人類の科学する心があった。そして技芸と技術が融合したとき、美的感動という新たな特性を伴う芸術としてのartが生まれた。 本シンポジウムでは、人間文化の原点である身体をartということばをキーワードとしてサイエンスする。 |
| 第1部 活動する身体 |
| ・ARTとしてのからだづくり |
| 石井直方 |
| ・作生成基盤としての体幹筋 |
| 金久博昭 |
| ・筋と動きをつなぐ腱 |
| 久保啓太郎 |
| ・立位姿勢のバランス制御 |
| 神崎素樹 |
| ・リズムを生み出す力学系 |
| 工藤和俊 |
| 第2部 表現する身体 |
| ・教養教育における‘からだ’の視点 |
| 古田元夫(東京大学副学長・理事/元大学院総合文化研究科・教養学部長) |
| 【要旨】人間の生活は、からだ、こころ、ことば、を基盤として成り立っており、東京大学の教養教育は、 これらの3要素が人間の基本的教養としてバランスよく修得できるよう配慮されることが望ましい。本シンポジウムでは、特に教養としての身体の意味を考える。 |
| ・巧みの技を科学する |
| 大築立志(生命環境科学系・身体運動科学) |
| 【要旨】人間は、動物としての動きを基に、労働、遊び、健康運動、コミュニケーションなどの新しい動きを考案し、 それらを洗練させた巧みな動きを使って文化を創造してきた。本シンポジウムでは、サイエンスから見た巧みな動きの文化特性を考える。 |
| ・世阿弥に学ぶ、からだとこころ |
| 松岡心平(超域文化科学専攻・表象文化論) |
| 【要旨】能の極意を記した花伝書等を通して、日本の伝統的身体運動文化としての舞におけるこころの表現とその技法について、 からだとの関連から再考する。 |
| ・脳画像で探る身心連携のART & SCIENCE |
| 跡見順子・桜井隆史(生命環境科学系・身体運動科学) |
| 【要旨】細胞が力学場で作りだした身体という制御可能な人間システムを同時的に稼働させ、こころを生起させる人間の身体の在りようを可視化する試みを紹介する。 身体文化を科学の言葉に変換し教育への導入の方策を探る。 |
| ・情報とからだ |
| 池上徹彦(文部科学省宇宙開発委員会委員/元産業技術総合研究所理事/元会津大学学長) |
| 【要旨】人と人の間の情報伝達は、身ぶりや表情、発話・書字などの身体による直接的表現と視覚・聴覚・皮膚感覚などの感覚によるその解読・理解を起源としている。 コンピュータやインターネットの発達から必然的に発生する情報と身体との遊離に含まれる問題点について考える。 |
| 総合討論 |
第13回身体運動科学公開シンポジウム(2005年度)
| 新しい教養教育としての身体運動とその科学的基礎 |
| 2006年3月5日(日)ポスター発表:9時-10時、シンポジウム:10時-17時30分 東京大学駒場キャンパス 数理科学研究科大講義室 |
| 第1部 平成18年度に向けた身体運動・健康科学実習授業への取組み |
| ・挨拶 |
| 木畑洋一(東京大学大学院総合文化研究科長・教養学部長) |
| ・身体運動関連カリキュラム改革の趣旨 |
| 跡見順子 |
| ・新共通基礎実習種目紹介 |
| 1.つもりと実際 大築立志 |
| 2.人間の基本動作 渡會公治 |
| 3.呼吸循環と健康 桜井隆史 |
| 4.身体運動と生命科学 跡見順子 |
| 5.救急処置 久保田俊一郎 |
| ・パネルディスカッション -新しい身体運動教育の意義を考える- |
| 内藤 耕(産業総合研究所経営調査室長・東京大学人工物工学研究センター客員助教授) |
| 梅景 正(東京大学保健管理センター医師) |
| 大場善次郎(東京大学工学教育推進機構教育プロジェクト室教授) |
| 浅間 一(東京大学人工物工学研究センター教授) |
| 板東久美子(文科省大臣官房審議官) |
| 中野滋文(厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長補佐) |
| 山本 泰(大学院総合文化研究科副研究科長・教養学部副学部長・教養教育開発機構教授) |
| 小島憲道(大学院総合文化研究科副研究科長・教養学部副学部長) |
| 第2部 特別講演「からだとこころ~21世紀の視点としての身体」 |
| 黒川清(日本学術会議会長) |
| 第3部 身体運動教育を支える身体運動・健康科学 (第13回身体運動科学シンポジウム) |
| ・運動習熟の基盤となる小脳シナプス可塑性 |
| 柳原大 |
| ・脳を育てる認知行動脳科学トレーニング |
| 小林寛道 |
| 身体・脳・環境の相互作用による適応的運動機能の発現 -移動知の構成論的理解- |
| 浅間一(東京大学人工物工学研究センター教授) |
| 運動は脳の細胞坂期は脳の細胞環境を良くする -良いストレスは悪いストレスを制する- |
| 跡見順子 |
| ・討論 |
第12回身体運動科学シンポジウム(2004年度)
(教育COL「からだとこころ」第5回研究会)
| 21世紀を支える科学・技術と身体 |
| 2004年12月1日(土)ポスター発表:11時30分-13時10分、シンポジウム:13時20分-18時30分 東京大学駒場キャンパス 数理科学研究科大講義室 |
| 主旨: 20世紀的な自然破壊=開発発展という価値観から、自然と人間の共生という21世紀的な価値観への転換にあたって、 保全されるべき「自然」の代表でありながら実は見落とされやすいものとして「人間」そしてその「身体」がある。 また、本来身体操作そのものであった技術が高度に発達した結果、社会の脱身体化が進行している。 豊かで持続可能な生活を実現するためには、自然環境を保全再生するための科学技術とともに、人間の身体や心のメンテナンスのための科学技術が必要である。 本シンポジウムでは、21世紀の科学技術と人間の関係を、身体を仲立ちとして考える。 |
| セッション1 身体運動の科学 |
| ・身体創造の科学と技術 |
| 石井直方 |
| ・身体メンテナンスの理論と実際 |
| 金久博昭 |
| ・身体運動を規定する要因?感覚と情動? |
| 村越隆之 |
| ・ヒトの行為の適応的多様性とその役割 |
| 工藤和俊 |
| ・ディスカッション |
| セッション2 科学・技術と身体 |
| ・(仮)21世紀の産業技術と身体の復権 |
| 吉川弘之(産業技術総合研究所/元東京大学総長) |
| 【要旨】地球環境の保全と再生、そこに暮らす人間およびあらゆる生物の保全は、 21世紀の最重要課題であり、そのために応用を視野に入れた新しい基礎研究の創成が求められている。 21世紀における新しい産業技術の方向と、人間の保全における身体の意義を考える。 |
| ・建築と身体感覚 |
| 加藤道夫(広域システム科学系/建築学) |
| 【要旨】人間と自然環境との間に介在する人工環境としての住居等の建築物は、 材質や立地とそこに住む人やそれを見る人の身体感覚、特に視覚と密接に関わっている。 視覚と建築の関わりを建築の図的表現法の変容の観点から振り返ることで、21世紀の建築と身体の関係を考える。 |
| ・<表現系>としての身体?想像的身体の変容? |
| 小林康夫(超域文化科学専攻/表象文化論) |
| 【要旨】人間にとっての身体とは、単に物理?生理的なものではなく、なによりもまず想像的なものである。 それ故、人間の行うあらゆる想像はかならず身体と結びついており、身体を欲望しており、身体においておこなわれる。身体は「わたし」の「形」なのである。 この想像的な身体が、メディア環境の劇的な変化のもとに大きく変容しつつある。その変容の本質を考えてみる。 |
| ・生命科学からみた健康と身体 |
| 跡見順子 |
| 【要旨】意欲に満ちた健康な生活は、適度なストレス刺激による身体の細胞の適応的機能向上によっている。 細胞活性化のための身体運動の科学的意義を考える。 |
| ・総合討論 |
第11回身体運動科学シンポジウム(2003年度)
| いのちとこころをつなぐ からだネットワーク ―ヒューマン・アクティヴィティ・リソースとQOLの向上を目指して- |
| 2003年11月29日(土)ポスター発表:12時50分-13時50分、シンポジウム:14時-17時30分 東京大学駒場キャンパス 数理科学研究科大講義室 |
| 主旨: 人間は、食べる・飲むなどの生命維持行為、歩く・走る・運ぶなどの移動や、持つ・操るなどの操作、描く・書く・話すなどの文化創造的自己表現行為を媒介として、 周囲の環境に働きかけながら日常生活を営んでいる。これらのいわゆる日常生活行為や行動は全て身体の動き、すなわち「運動」である。 運動は、環境との相互作用の手段として、特にヒトを含む動物にとっては必要不可欠の生命活動であると同時に、また、自己の心を表現し他者とのコミュニケーションを行うための有力な手段でもある。 本シンポジウムでは、生命科学、心理学、身体運動科学、社会学等、種々の角度からhuman activity resourceとしての身体運動を再考し、 QOL(quality of life)レベルの高い精神的・身体的・社会的に健康なアクティヴ・ヒューマン・ライフの基盤確立の方策を探る。 |
| ・運動と脳 |
| 大築立志 |
| 【要旨】ヒトの生活を構成するさまざまな身体運動=骨格筋活動は、脳・神経系の巧みなコントロールを受けて遂行されると同時に、 脳・神経系の知的機能をも向上させる効果があるという最新知見を紹介する。 |
| ・こころとからだ-進化心理学の最近の研究から |
| 長谷川寿一(大学院生命環境科学系認知行動科学:進化心理学) |
| 【要旨】チンパンジーと幼児の仲直り行動、自閉症児の他者認知、死亡率の性差、殺人率などに関する研究から、こころとからだの関係を考える。 |
| ・社会の中の身体 |
| 山本泰(大学院国際社会科学専攻:社会学) |
| 【要旨】社会行動の基礎としての身体やその動きと、舞踊、演劇、テレビ、映画などの身体表現を媒介とする芸術がもつカタルシス効果による社会の安定などについて、身体と社会という観点から考える。 |
| ・細胞運動の原点-運動システム進化の一つの見方- |
| 大森正之(大学院生命環境科学系基礎生命科学:植物生理学) |
| 【要旨】生物の生命活動エネルギーを光合成によって産生する植物の葉緑体、 およびその進化的起源である藍藻には、実は運動能力がある。細胞の運動とは何かを、運動のためのエネルギー供給系を含めて考える。 |
| ・身体運動の原点-‘運動生命科学’の提唱- |
| 跡見順子 |
| 【要旨】骨格筋や心筋をはじめあらゆる細胞は、適度なストレス刺激によって適応的に機能を向上させる。 細胞活性化に不可欠な刺激としての運動の意義を考える。 |
| ・運動による生活習慣病の予防と治療 |
| 久保田俊一郎 |
| 【要旨】文明の進歩による生活習慣の変化は、便利さと引き換えに身体の劣化をもたらしている。生物としてのヒトの機能を回復維持するための運動の効果を探る。 |
| ・総合討論 |
身体運動科学シンポジウム第10回記念大会(2002年度)
| 行動する身体と心 -21世紀を支える身体運動の科学- |
| 2002年11月30日(土)9時-18時20分 東京大学駒場キャンパス 数理科学研究科大講義室 |
| 主旨: 新しい未来を切り拓く活力に溢れた日本人としての行動指針がいまこそ求められている。行動する中で身体が活性化し、こころが生まれる。 生命科学をはじめとする人間を含むいきものの「理」を追求する回路にのせれば新しい道が拓ける。 10周年を記念して身体運動科学研究室全教官が勢揃いし、 21世紀において運動やスポーツが育む行動する人間の「理」を語り、工学・医学との連携を探る。 また、行動する人間の知の構造化と表出と題して前工学部長小宮山宏氏に特別講演を御願いし、21世紀を展望する新しい枠組みを提案していただく。 |
| シンポジウムI 動く身体を支える細胞と個体のしくみ |
| ・肝機能と骨格筋の肥大 |
| 山田茂 |
| ・運動適応にみる器官・細胞のクロストーク |
| 石井直方 |
| ・細胞と個体のストレス適応連関 |
| 跡見順子 |
| ・乳酸と運動 |
| 八田秀雄 |
| ・前頭葉による歩走の制御 |
| 久保田競(日本福祉大学・脳生理学) |
| ・リハビリテーションと人間の回復力 |
| 福林徹 |
| ・機械的刺激を導入した再生医工学 |
| 立石 哲也 (東大工学部・再生工学) |
| 特別記念講演 |
| ・動け!日本-知の構造化と表出 |
| 小宮山宏(「工学部教育プロジェクト室」室長、前工学部長 化学システム工学科教授) |
| シンポジウムII スポーツ:脳と身体を結ぶ「理」の回路 |
| ・ヒト骨格筋の収縮中における筋線維と腱のふるまい |
| 川上泰雄 |
| ・不活動が身体に及ぼす影響 |
| 金久博昭 |
| ・予防医学から身体運動科学へボディーアウェアネス |
| 渡會公冶 |
| ・身体の力学的出力特性とスポーツ |
| 深代千之 |
| ・打動作の体幹の回転の仕組み(野球・ゴルフなど) |
| 小嶋武次 |
| ・スポーツの上達に生かす力学の基本法則 |
| 兵頭俊夫 |
| ・スポーツを進化させる運動シミュレーション |
| 姫野龍太郎(理化学研究所・情報環境学) |
| ・巧みな動きと脳の働き |
| 大築立志 |
| ・認知動作型トレーニングマシーン:動作における自己対話 |
| 小林寛道 |
| 総合討論 |
第9回身体運動科学シンポジウム(2001年度)
| 脳と生命に働きかけるスポーツサイエンス |
| 2001年6月9日(土)ポスター発表:13時-13時45分、シンポジウム:13時55分-18時30分 東京大学駒場キャンパス 11号館1106号室(シンポジウム会場)、1103号室(ポスター発表会場) |
| 脳と運動・スポーツは切っても切れない関係にあります。自分の意志で行うすべての運動・動作・行動は、すべて脳の指令による骨格筋の収縮、 すなわち随意筋収縮(Voluntary Contraction)によるものです。とりわけスポーツを含む身体活動はすべての身体機能を動員して行われる究極的な随意筋収縮の表れです。 かつて自然の中をかけめぐり、遊びやスポーツに興ずることで子どもは成長しました。畳の上の日常生活での布団の上げ下ろしや立ち居振る舞い動作の中で、 高齢者も否応なく身体の活動性を上げていました。身体を使い、身体で学習する生活や社会があったのです。脳は、からだと環境との相互作用により形成されてゆくものであり、 からだを通しての実体験は計り知れないほど大きな意味をもっています。特に、随意的筋収縮による身体運動は実体験を得るための最良の手段です。 自分のからだを動かして理解することで、様々な問題を有機的につなげる主体的な概念形成ができるのです。 数年前、豊富な自発活動が可能な環境が、神経細胞の増殖を促進するという研究がSalk Instituteから発表されました。 次いで一昨年Nature Neuroscienceにおとなのマウスによる回転かごでのランニングが脳の神経細胞の増殖と神経分化を促進するという研究が発表されました。 また、実際に高齢者の有酸素運動が記憶能力を改善させるという研究をTime誌が取り上げ、世界的規模で身体運動と脳との関わりが注目されはじめています。 全身を活性化し、脳機能を身体運動の中で発揮する運動を科学的に理解する時代になっています。運動やスポーツは21世紀の人の生命にかかわる大きな問題を解決する糸口になると思います。 今回は「出力依存性の脳」という仮説を提出していらっしゃる理化学研究所の松本元先生にシンポジウムにご参加いただきます。多くの方々のご来場を心よりお待ちしています。 |
| 1. 巧みな運動を創り出す要因を探る |
| ・巧みな動作の制御から見た脳の働き |
| 大築立志 |
| ・野球のバッティングの力強さとミート力 |
| 小嶋武次 |
| ・立体幾何図形にもとづく動作イメージの構成とトレーニング |
| 小林寛道 |
| 2. 随意筋出力から脳を探る |
| ・随意最大努力下での筋力 |
| 福永哲夫 |
| ・協働筋の活動交替の発現要因 |
| 神崎素樹 |
| ・運動時のヒト骨格筋の機能マッピングから脳の働きを考える |
| 秋間広 |
| コーヒーブレイク&ストレッチング(渡會公冶) |
| 3. 随意性の背景 |
| ・脳が筋を動かし、筋が脳を動かす |
| 石井直方 |
| ・動物細胞の動的必然性をさぐる |
| 跡見順子 |
| 4. 出力依存性の脳と運動 |
| ・脳の新しい科学と生命を育む二大原理-出力依存性とメモリー主体型- |
| 松本元 (理化学研究所脳科学総合研究センターブレインウェイグループディレクター) |
| 総合討論 |
第8回身体運動科学シンポジウム(2000年度)
| 最新の筋力トレーニング方法とその科学的背景 |
| 2000年6月10日(土)ポスター発表:12時30分-13時30分、シンポジウム:13時40分-16時40分 東京大学駒場キャンパス 1313教室 |
| 毎年行っている身体運動科学シンポジウムは、今年で8回目を向かえます。 今年は最新の筋力トレーニング方法とその科学的背景]をテーマに下記の日程で行います。奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。 |
| ・筋力トレーニングの歴史 |
| 山田茂 |
| ・筋力トレーニングと筋?腱複合体の動態 |
| 福永哲夫 |
| ・筋力を発揮しない筋力トレーニング |
| 石井直方 |
| ・認知動作型パワーアップトレーニングマシンの開発法 |
| 小林寛道 |
第7回身体運動科学シンポジウム(1999年度)
| スポーツバフォーマンスを高める知と技とカ -Part2- |
| 1999年6月5日(土)13時~16時30分 東京大学駒場キャンパス 1314教室 |
| ・スポーツパフォーマンスと脳内情報処理過程 |
| 平工志穂 |
| ・卓球のフォアハンドストロークにおける下肢の役割 |
| 小嶋武次 |
| ・安静立位の姿勢制御 |
| 政二慶 |
| ・スプリントマシンを用いたトレーニング内容と競技成績 |
| 杉田正明 |
| ・腱は伸びるか?力学特性、MRIよりの解明 |
| 福林徹 |
第6回身体運動科学シンポジウム(1998年度)
| スポーツバフォーマンスを高める知と技とカ |
| 1998年6月13日(土)14時より 東京大学駒場キャンパス 1106教室 |
| ・筋形状からヒトの発揮筋力を考える |
| 川上泰雄 |
| ・重量物挙上トレーニングの可能性と限界 |
| 金久博昭 |
| ・走運動の「技」の成り立ち |
| 小林寛道 |
| ・身体知としての動きと力の制御機構 |
| 大築立志 |
| ・センサーの調節と障害予防 |
| 渡會公治 |
第5回身体運動科学シンポジウム(1997年度)
| 疲労を科学する |
| 1997年6月21日(土) |
| 演者:和久貴洋、八田秀雄、福林徹、川原貴、小林寛道 |
第4回身体運動科学シンポジウム(1996年度)
| ストレッチを科学する |
| 1996年7月13日(土)14時~17時 東京大学駒場キャンパス 1106教室 |
| 身体運動は骨格筋の収縮力が腱を介して骨に伝達されることによって生じる関節回りの骨の回転遲動である、一般には骨格筋は収縮すれば短縮し、 その筋の両端に付着している骨が互いに近づく方向の運動が生じる。しかし、実際の運動場面では,身体に加わる力の大きさや運動の性質によっては、筋が収縮しつつ伸張(Stretch)する場合も多い。 過度の伸張が筋腱の障害を引き起こすこともある。また、身体には、ある方向の運動を引き起こす筋に対応して、それと反対方向の運動を引き起こすような関係にある筋(拮抗筋)が存在し、 一方が短縮すれば他方は伸張する。筋伸張を刺激として生じる伸張反射は、このような拮抗筋関係を利用して、立位姿勢の保持や運動軌道の誤差修正に重要な役割を果たしている。 さらにまた、近年、機械的伸張が骨格筋細胞の萎縮や発達に大きな影響を与えることが、生化学的な研究によって明らかになりつつある。このように、身体運動を考える場合には、 筋の短縮ばかりでなく、筋の伸張も考慮する必要があるという観点から、本シンポジウムでは筋とそれに付随する腱の伸張(ストレッチ)に焦点を当て、身体運動における筋腱伸張のさまざまな側面を検討する。 |
| ・伸張性筋収縮の生理学的メカニズム |
| 石井直方 |
| ・ストレッチとエネルギー代謝 |
| 山田茂 |
| ・身体運動におけるstretch reflexの役割 |
| 大築立志 |
| ・跳躍動作における筋腱ストレッチの効果 |
| 深代千之 |
| ・腱を構成する蛋白質の構造と機能 |
| 水野一乗 |
| ・ストレッチによる遺伝子発現の機構を考える |
| 跡見順子 |
| ・ストレッチとスポーツ障害 |
| 渡會公治 |
第3回身体運動科学シンポジウム(1995年度)
| 生命科学から身体運動を解明する -骨格筋の適応機構を細胞・分子・遺伝子から考える- |
| 1995年6月24日(土) |
| 演者:石井直方、跡見順子、山田茂 |
第2回身体運動科学シンポジウム(1994年度)
| スポーツバイオメカニクスからみた動きの巧みさ |
| 1994年6月21日(土) |
| 演者:深代千之、船渡和男、小嶋武次、大築立志、渡會公治 |
第1回身体運動科学シンポジウム(1993年度)
| ヒトの筋のダイナミックス |
| 1993年6月22日(土) |
| 演者:福永哲夫、久野譜也、石井直方 |