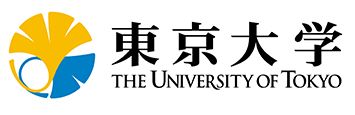授業
基礎生命科学実験:実験17「骨格筋の力学的性質」
1. 受講の前に
- 受講者は,あらかじめこのページに掲載されている内容を確認しておくこと。
- 授業実施日の12時10分までに,教科書p175に記載の予習課題をノート(電子ノートも可)に解いて,スキャンした電子ファイルをUTOLを介して提出すること。
- また、提出した後,提出したファイルが意図したものであることを必ず確認すること。 この確認と再提出に必要となる時間も見込んで,〆切時刻に対して余裕をもって最初のファイルの提出を行うこと。提出〆切後のファイルの差し替えは認めない。
- サーバ・クライアント,その間のネットワークの状況等によって,UTOL上の操作とシステムの応答に秒単位の遅れが生じることが無いわけではない。したがって,〆切直前に提出することは極力避けること。このことによる提出遅れも正当な理由とはならない。
2. 授業の実施形態について
各グループの学生をさらに2つのグループに分けて,それぞれ3限と4限に実習を行う。いずれも105分授業で行い、3限、4限の開始時刻はそれぞれ13:00と14:55である。遅刻しないよう注意すること。30分以上の遅刻は「欠席」扱いとする。
学生のグループ分け(3限と4限のどちらで実習を行うか)は決定し次第,UTOLに掲載する。実習を行わない時限(3限に対面で実習を行う学生では,4限)は,予習あるいはレポートの作成にあてること。
3. 欠席の申請について
実験補遺の1.一般的な注意事項の【体調不良等による欠席】を参照のこと。
4. 実験について
以下の項目について,データの取得・解析,考察を必須とする:
1)肘関節角度を 50 度から 150
度までの範囲で変え,それぞれの関節角度における等尺性収縮張力(肘関節回転力)を測定する。測定結果から,肘関節角度-張力関係および肘屈筋の長さ-張力関係を導く。
2)等尺性最大張力以下のさまざまな大きさの負荷をかけて等張性収縮をおこなった時の,それぞれの負荷での肘関節屈曲角速度を測定する。測定結果から肘屈筋の力-速度関係を求め,最大短縮速度を導く。
3)1 および2の結果をカエル骨格筋単一筋線維の結果と比較検討する。
5. レポートについて
5.5.1 提出について
以下の注意事項に従うこと。
- ほかの種目と記載すべき事項及び提出の〆切が異なるので,十分注意すること。
- レポートは,UTOLを介して提出すること。
- 提出〆切は授業実施日の1週間後の19時00分とする。〆切を厳守すること。〆切に遅れたレポートは,長期の入院や忌引きなど特別な事情がある場合を除いて受理しない。とくに,PCやその他機器の不具合や通信環境の不調(UTOLの障害を除く)は提出遅れの正当な理由とはならない。
- UTOLに提出した後,提出したファイルが意図したものであることを必ず確認すること。この確認と再提出に必要となる時間も見込んで,〆切時刻に対して余裕をもって最初のファイルの提出を行うこと。提出〆切後のファイルの差し替えは認めない。
- サーバ・クライアント,その間のネットワークの状況等によって,UTOL上の操作とシステムの応答に秒単位の遅れが生じることが無いわけではない。したがって,〆切直前に提出することは極力避けること。このことによる提出遅れも正当な理由とはならない。
- 不十分な内容であっても一旦提出し,期限内に再提出することは全く問題ない。再提出の際は,古いファイルは消して新しいファイルに置き換えること。
5.5.2 不正行為のチェック,体裁,記載すべき事項等について
本実験で提出するレポートは定期試験と同等の意味をもつ。従って,剽窃等の不正行為については専用のソフトウェアなども用いて入念にその有無をチェックする。その結果,不正行為が認められた場合は,協力者も含め
厳しい処分を行う。不正行為には,インターネット上から得られる情報の注記なしの借用や,友人等から提供を受けたレポートからの書き写しや図表の借用も含まれる。
体裁は以下のとおりとする。
- A4サイズのPDFファイル
- ファイル名は氏名_学籍番号_骨格筋.pdf(例:駒場太郎_J5240XXX_骨格筋.pdf)とすること。
- 可読性の観点からワープロソフトの利用を推奨する。ただし,手書きで作成したものをPDFファイルに変換して提出することも可。最終的に1つのPDF ファイルとして提出すれば,図表など一部が手書きでも問題ない。
構成は以下の通りとする。
A)目的,方法,結果,考察の順に書くこと。各項には必ず本文を記載すること。
B)「目的」目的のない実験はあり得ない。本実験によって何をどこまで明らかにしようとするのかを自分の言葉で書くこと。また,目的を明確にするために理論的背景を自分の言葉で書くこと。
C)「方法」教科書をよく読んで,自分が実際に行った実験方法の要点を簡潔にまとめて書くこと。なおこの項は,自分が行ったことを記述するためすべて過去形で記述すること。
D)「目的」・「方法」の内容は全員に共通するが、自分の言葉で書くこと。教科書の記述や他人が書いたレポートを丸写ししたもの(ほぼ同じものを含む)は評価しない。
E)「結果」生データのみでなく,取得したデータを解析および整理した図表をこの項で示すこと。図表が何を示すものであるか,図表から何がわかるかについて記すこと(下記の“図表”を参照)。“Analysis”の図を使用してはならない。
F)「考察」実験レポートには実験結果に関する考察が必要である。この実験においては、教科書に記載の課題1,3,4,5,6に解答することに代える。
G)「図表」図と表にはそれぞれ通し番号をつけること(図は下に,表は上に)。図の縦軸と横軸には目盛りと単位を必ずつけること。表の場合も必ず単位をつけること。
H)実験 2 のデータを非線形回帰して,Hill 定数を求めるためのエクセルファイルが UTOLからダウンロードできる。このファイルを利用して作成した図をレポートに使用してよい。積極的な利用を推奨するが,レポート作成する際に必ず利用しなければならないということではない。
I)「その他」文献値や先行研究の結果を引用した場合は必ず出典を明記すること。意見・感想がある場合はレポートの最後に簡潔に記載すること。
6. その他
予習としては教科書 pp. 171~185 の内容をよく読んでおくこと。エルゴメータやPCなど実験機器は指示があるまで操作しないこと。