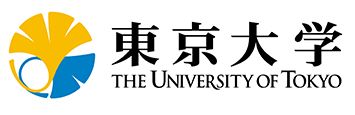研究
第33回身体運動科学シンポジウム 報告記
令和7年11月29日(土)、東京大学駒場Ⅰキャンパス18号館ホールにて、第33回身体運動科学シンポジウム/第229回生命環境科学系セミナー「ジュニアから高齢者までを見据えたスポーツ医学の最前線」が開催された。本シンポジウムでは、成長期の運動器障害からトップアスリートの競技支援、高齢者の運動器疾患の病態解明や治療戦略、さらにデジタル技術を活用した未来の医療・リハビリテーションまで、多様な視点からスポーツ医学の現在と将来の展望が議論された。特に今回は、長年にわたりスポーツ医学研究・臨床、および身体運動科学研究室の発展に尽力されてきた福井尚志先生の退官記念講演でもあり、福井先生とゆかりのある研究者が演者として登壇した。
第1部では、門口智泰先生(東京大学大学院総合文化研究科 助教)から、サルコペニアの発症・進行に関与する要因に着目した研究が紹介された。サルコペニアは加齢に伴う骨格筋量・筋力の低下を特徴とし、特に心血管疾患患者ではフレイルを合併することで機能低下が加速し、生存率低下にもつながることが示されている。講演では、サルコペニアを進展する機序について、とりわけ活性酸素種(ROS)とミトコンドリア機能障害に焦点が当てられた。心血管疾患モデルマウスでは、筋重量および筋線維断面積の減少、タンパク質代謝関連因子の変化、ミトコンドリア酵素活性低下、ROS産生亢進、抗酸化シグナルであるNRF2の低下が認められた。一方、細胞内でROSを産生する酵素であるNADPHオキシダーゼ4(NOX4)を欠損させたマウスでは、これらが抑制され、NOX4が心疾患関連骨格筋萎縮の制御に関与する可能性が示された。続いて老齢マウスの解析では、酸化ストレス増加とミトコンドリア機能低下に加え、脂質代謝産物の増加が認められた。また、変形性膝関節症(膝OA)の進展に肥満が密接に関与していることから、外科的手術により膝OAを誘導したマウスにおいて、さらに肥満を誘導した条件で実験を行った。その結果、膝OAに伴う関節病変の進行に加え、筋重量および下肢筋力の低下が確認され、肥満がこれらの変化を助長することが明らかとされた。講演の結びとして、ROSは疾患モデルでは骨格筋萎縮を促進する一方、運動適応においては持久力向上に寄与する側面も持つため、必ずしも一律に抑制されるべきではないと前置きした。そのうえで、NOX4を介した酸化ストレス亢進とミトコンドリア機能障害が骨格筋萎縮に関与し、NOX4がサルコペニア治療の分子標的となり得ることが示された。
続いて、今井一博先生(東京大学大学院総合文化研究科 准教授)から、ジュニアトップアスリートを対象としたスポーツ損傷の疫学調査に基づく知見が紹介された。成長期は骨端線を含む骨組織が脆弱であり、適切な力学的刺激は骨量増加に寄与する一方、過度な負荷や反復動作により骨端症や疲労骨折が生じやすい背景が説明された。特に小学校高学年から中学生にかけては、急激な成長と筋力・技術の不均衡により損傷リスクが増大することが示された。ゴルフ選手(11〜17歳)の調査では損傷部位として腰部が最多で手関節が続き、全国レベルのバドミントン選手(7〜12歳、611例)では膝関節・足関節損傷が最多であった。また、年齢上昇とともに損傷率は増加する一方、競技歴が長い群では損傷率が低下するため、技術習得が損傷予防に寄与する可能性が示された。さらに、複数競技のジュニア選手を対象とした解析では、1日2.5時間以上・週15時間以上の練習量は肩痛などのリスク増加と関連していた。講演の結びでは、スポーツ損傷予防には発生率把握、原因分析、介入、効果検証の循環的アプローチが不可欠であり、データ蓄積と競技団体・学会との連携を通じて、選手が生涯にわたり安全に競技を継続できる環境を整える重要性が述べられた。
中田研先生(大阪大学大学院医学系研究科 教授)からは、膝関節障害の治療・再生医療研究、スポーツ現場におけるパフォーマンス評価、そしてヘルスプロモーションに関する取り組みが紹介された。中田先生は、遺伝子異常モデルマウスを用いて関節軟骨・椎間板変性の分子基盤を解明し、その後は前十字靭帯損傷や半月板損傷に対するバイオメカニクス研究と手術手技の改良に取り組んできた。特に、従来切除されていた半月板病変に対し、アテロコラーゲンスポンジを用いた再生誘導材を開発し、動物実験から臨床試験まで進展させた点が紹介された。一方、東京オリンピックに向けては「サイバーフィジカルシステム for スポーツ」の概念のもと、ウェアラブルデバイスを活用して日々の運動強度とそのばらつきが選手の故障リスクや競技成績と関連することを示したほか、暑熱下での体温・心拍モニタリングや不整脈検出、シューズ内センサーによる術後歩行解析など、競技現場から臨床リハビリまで応用可能なデータ統合システムの開発が紹介された。現在はこれらを就労世代や高齢者へ応用し、デジタルツインを活用した次世代コンディショニング支援システムの構築が進められている。講演の締めくくりとして、スポーツを「健康に資するあらゆる身体活動」と捉え、データ駆動型ヘルスプロモーションを通じてライフパフォーマンス向上に貢献する重要性が述べられた。
第2部では、福井尚志先生(東京大学大学院総合文化研究科 教授)による講演「私の軌跡と現在地」が行われ、柔道中の受傷をきっかけに整形外科医を志した経緯、大学病院での臨床経験、スポーツチームドクターとしての現場経験、そして長年にわたり取り組んできた膝OAの病態解明の研究の歩みが紹介された。特に、従来主流であった細胞・動物モデルによる基礎研究だけでは、患者の体内で実際に起こっている現象のすべてを説明しきれないのではないかという問題意識から、手術時に得られる関節軟骨、滑膜、関節液といったヒト臨床検体を用いた研究へと舵を切った背景が語られた。講演では、損傷した関節軟骨に荷重が加わることで血管内皮増殖因子A(VEGF-A)や線維芽細胞増殖因子1(FGF-1)といった因子が放出され、滑膜血管の増生や透過性亢進が生じ、血漿成分が関節内に流入し、滑膜表層にフィブリンが形成される仕組みが示された。その後、線溶反応によって生じるプラスミンが軟骨分解酵素MMP-1を活性化させ、急速な軟骨破壊や滑膜変化を引き起こす可能性が提示された。これは炎症を主因として理解されてきた膝OAの進行を、凝固・線溶系という一般的な生体反応の局所的過剰活性として捉え直す新たな視点を示すものであった。さらに、その機序に基づき、関節内でのフィブリン形成および線溶反応を制御する既存薬の適用可能性についても検討が進められていることが紹介された。福井先生は、「大学教員には定年があるが、研究者に定年はない」という言葉を引用し、研究成果を将来的に患者治療へ還元していきたいとの思いを述べて講演を締めくくった。ヒト臨床検体を対象とした研究は、実験条件を統制しやすい基礎研究に比べて制約が多く、論文評価や研究費獲得の面で不利となることもある。しかし一方で、基礎研究のみでは捉えきれない“実際の体内で起こっている現象”を理解するうえで重要な役割を担う領域でもある。福井先生は、基礎研究と臨床研究を往復しながら病態の本質に迫ろうとする姿勢を一貫して示しており、その背景には「患者のためになる研究でなければ意味がない」という明確な信念があることがうかがわれた。また、研究や論文の評価指標の大小にとらわれず自分が何を大切に研究していくのかを問い続ける姿勢は、学生や若手研究者に対して、今後の研究活動の在り方を考えるうえで指針を示してくれるものであったと感じた。
以上、本シンポジウムでは、スポーツ医学を基盤として、基礎研究・臨床・疫学的視点、さらには工学応用や現場実践の観点が共有され有意義な議論が展開された。最後に、参加者の皆様ならびに企画・運営に尽力いただいた関係者の皆様に、心より御礼申し上げる。
(執筆:身体運動科学研究室 助教 田名辺陽子)